生活の木70周年|原宿の小さな陶器店から始まった香りの物語

こんにちは、IRISEE22です 。
今回は、以前からお世話になっているアロマショップ「生活の木」についてご紹介したいと思います。最新の情報を知るために、久しぶりに店舗を訪ねてみました。
スタッフの方からは、アロマ検定のテキスト(1級・2級)が1冊にまとまったことや、精油のパッケージが新しくなったこと、さらに検定試験がオンラインで受けられるようになったことなど、最近の変化をいろいろ教えていただきました。
久しぶりにアロマのお話をしながら、お店に広がる香りに包まれていると、当時は夢中でアロマを学び、香りを楽しんでいた頃の自分をふと思い出しました。香りはテキストで学んだように“記憶と深くつながっている”という言葉を改めて実感!
そして会話の中で、生活の木が今年で創業70周年を迎えることを知り、頂いた情報誌を読みながら、気になって自分でも調べてみると、そこには、香りを通じて日本の暮らしに“自然の心地よさ”を届け続けてきた長い歩みとたくさんの想いが詰まっていました。
1955年:原宿で陶器店「陶光」として創業
生活の木の歴史は、1955年(昭和30年)、現在の原宿・表参道で開かれた陶器店「陶光(とうこう)」から始まりました。当時は、外国人観光客向けに日本の陶器を販売していたお店で、美しい器を通して日本の文化や手仕事の魅力を伝えていたそうです。
この原宿・表参道の場所は、現在も変わらず生活の木 原宿表参道店として続いており、創業の地が今もブランドの象徴になっています。
1970〜1980年代:ハーブと香りとの出会い
時代が進むにつれ、生活の木は陶器だけでなく、海外のライフスタイルや自然の恵みに関心を広げていきます。
1970年代には、アメリカからポプリやハーブ素材の輸入をスタート。
1983年にはオリジナルハーブティーを販売、1984年にはエッセンシャルオイル(精油)やハーブソープ、ハーバルバスなど香りを暮らしに取り入れる商品を次々と展開していきました。
そして1986年、社名を「有限会社 生活の木」に変更。翌年の1987年には、日本で初めて「アロマテラピー」を本格的に提案し、今から約38年前という早い時期から、香りを取り入れた“癒しの文化”を日本に広げていきます。
この頃から、生活の木は「自然・健康・楽しさ」をテーマに、香りを通して心と体を整えるライフスタイルを提案するブランドへと発展しました。
1990年代:世界の生産地とつながる
1990年になると、生活の木はスリランカに現地法人を設立。現地の人々と協力しながら、ハーブや精油の原料づくりを始めます。
これにより、原料の品質管理や安定供給を自社で行えるようになり、さらに1993年には「株式会社 生活の木」へと組織を拡大。
そして1995年、スリランカ・キャンディに「Hotel Tree of Life(ホテル・ツリー・オブ・ライフ)」を開業。このホテルは、アーユルヴェーダやハーブなど自然の力を体験できる滞在型施設として運営されており、生活の木の理念である「自然とともに生きる」姿勢を、現地の文化とともに体現する象徴的な場所となっています。
“原料を育てる人・届ける人・使う人”のすべてが豊かになるように~そんな想いが、この時代に確かな形として実を結びました。
2000年代:香りを「学び、体験する」場所へ
2000年代には全国にショップやスクールが広がり、アロマやハーブを気軽に学べる場所として親しまれるようになりました。
生活の木は、ただ商品を販売するだけでなく、香りの楽しみ方を伝える場所として進化。アロマテラピー検定のテキストや講座なども多くの人に支持され、香りを学ぶ文化が日本に根づいていきました。
お店でスタッフの方に香りのことを教えてもらったり、スクールでブレンドを学んだり。そんな時間が、今も多くの人の記憶に残っているのではないでしょうか?
私も、その中のひとりです。
2020年代:自然と共に歩む香りづくり
近年では、サステナブル(持続可能)なものづくりにも力を入れています。
埼玉県飯能市には、ハーブガーデンを併設した「薬香草園(やっこうそうえん)」を運営。植物に直接触れ、自然のリズムを感じながら香りを学べる場所として人気を集めています。
また、岐阜県瑞浪市には製造・物流拠点があり、国内生産による品質管理や環境への配慮を徹底。2024年には精油のパッケージデザインが新しくなり、現代のライフスタイルに合わせた新しい香りの提案を続けています。
どの時代も変わらないのは、“自然と人が心地よく共に生きること”を大切にしていること。その想いが、生活の木のすべての製品に息づいています。
社長の言葉:「志事(しごと)」という想い
生活の木の代表取締役社長・重永 忠さんが大切にしている言葉に、私はとても共感しました。それは、仕事の「仕」ではなく、**“志”の字を書く『志事(しごと)』**という考え方です。
「志や思いがなければ、それはただの作業。
心を込めて取り組むことで、初めて“志事”になる。」
この言葉が、生活の木の企業文化の中にしっかりと息づいています。
お店のスタッフの方々が一人ひとり温かく、丁寧に対応してくださるのも、
この“志事”の想いが根底にあるからだと感じます。
まとめ:香りは、心のとまり木
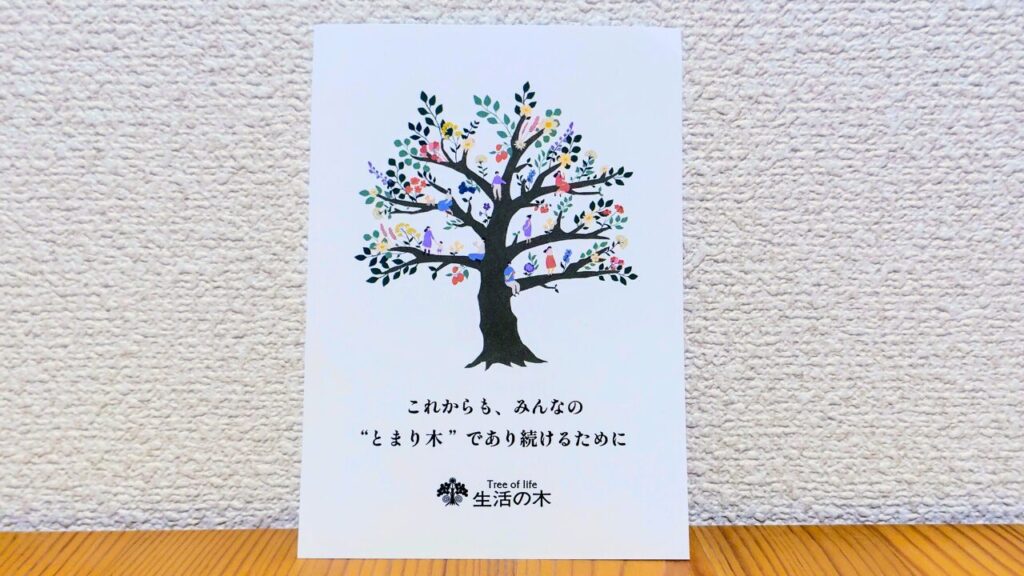
1955年に原宿で生まれた小さな陶器店が、70年の時を経て、いまや日本中に「香りのある暮らし」を届ける存在になりました。
香りは、目には見えないけれど、どんなときもそっと心を包み込んでくれるもの。
日々の暮らしの中で、少し疲れたとき、嬉しいとき、ふと深呼吸したくなる瞬間に—生活の木の香りが“とまり木”のように寄り添ってくれたら、それはとても素敵なことだと思います。
香りがあるだけで、暮らしはやさしく整う。
それが、70年を超えても変わらない生活の木のメッセージだと私は思いました。
では、今日はこのへんで。ブログを読んで頂きましてありがとうございました。
生活の木公式サイト(https://corp.treeoflife.co.jp/)
Hotel Tree of Life 公式サイト(https://hoteltreeoflife.com/)

